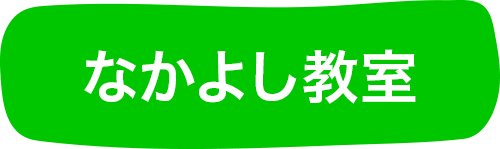勉強やスポーツなどで成果を出すには、一つのことに黙々と集中する力が必要です。
でも「うちの子は、集中力がない」「すぐに飽きてしまう」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、子どもの集中力を養う方法についてお伝えしていきたいと思います。
集中力が育つのは、幼児期
集中力は、非認知能力の一つ
「非認知能力」という言葉をご存知でしょうか。
非認知能力とは、学力やIQのように数値化できるものではなく、大きく分けると「自分自身をコントロールしていく力」「自分以外のだれかとコミュニケーションする力(社会性)」があります。
中でも今回は「自分自身をコントロールしていく力」に焦点をあててお伝えしていきますが、具体的には
・意欲を持って、取り組む
・粘り強く、物事に取り組む
・失敗から学ぼうとする
・自分を信じることができる
などの力が、挙げられます。
集中力も非認知能力のひとつで、「深く集中する」「集中を持続させる」には、自分自身をコントロールする力を養っていく必要があります。
自分をコントロールするなんて、小さな子どもにできるの??と思われるかもしれませんが、子ども時代こそ伸びやすい時期なのです。
▼関連記事
非認知能力が身につく自然遊び
幼児期は、非認知能力が伸びやすい時期
幼児期は、非認知能力の土台を育みやすい時期です。
非認知能力を育むポイントは「あそび」や「チャレンジ」にあるのですが、
幼児期の子どもは、日常のちょっとした物事にも、好奇心を働かせてあそびにしてしまう「あそびの天才」であり、
新しいことに対して「やってみたい!」とチャレンジ精神を発揮する時期でもあります。
非認知能力を育むには最適な時期と言えるので、「まだ小さな子どもだから・・・」と尻込みせずに、やりたいことはやらせてあげるようにすると良いでしょう。
集中力を伸ばすあそびとは?

つみき、パズル、折り紙などの手先を動かすあそびがおすすめ
「指は第二の脳」と言われるほど、指先を多く使うことで脳の広範囲を刺激することができます。
手指の器用さを「巧緻性(こうちせい)」と呼びますが、物をつかんだり、並べたり、積み上げるなど、巧緻性を高めるあそびは「集中力」「思考力」などが向上すると言われています。
例えば、
●つみき
●パズル
●折り紙
●あやとり
●ビーズあそび
などは、手を使ってあそぶので、巧緻性が高まり、集中力アップにもつながります。
できたものをお父さん、お母さんに見せることができるので、「自分でできた!」という感覚を体験することもできます。
「自分でできた」という体験によって、より深く集中して取り組むようになるので、小さいうちからそのような体験を積ませてあげられると良いですね。
▼関連記事
指先を動かすことで、脳が育つ!巧緻性の重要性
遊びながら賢い子に育つ!つみき教育
好きなこと、興味のあることはとことんやらせてあげる

子どもの集中力を伸ばそうと思うなら、目の前の物やできごとに対して、興味を持ったり、面白いと思えることが大切です。
学生の頃を思い出していただきたいのですが、好きな教科は集中して授業を聞いていたけど、興味のない教科は眠くなったり先生の話をあまり聞いていなかった・・・ということはないでしょうか?
これは、好きだと思うことには脳がよく働き、そうではないものに対しては脳があまり機能しない、という脳の仕組み上、ごく自然な現象です。
なので、好奇心を持てること=集中して取り組めることだと言えます。集中して取り組むことで、成果を出すことができれば、「もっとやろう!」という意欲も育っていきます。
危ないことを除いて、好きなこと、興味のあること、好奇心を持てることは、どんどんやらせてあげてください。
また、子どもと接する上で
●子どもが「これって何?」「なんで、こうなっているの?」と質問をしてきたことには、なるべく丁寧に答えてあげる。
●子どもが興味を持っていることに対して、関心を持つ。
という2点も、心がけてみてください。そうすることで、子どもは、安心して目の前のことに取り組むことができます。
▼関連記事
好奇心旺盛な子どもほど、ぐんぐん脳が育つ!
頭の良い賢い子を育てるポイントは「好奇心」
集中力を高めて、総合力の高い子に!
冒頭でもお伝えしたように、集中力は、勉強・スポーツなど、何をやるにも欠かせない力です。
集中力がある子は、総合的に能力を発揮できる子なので、どんな分野に進んでも良い成果を残すことができます。
幼児期のうちから、たくさんのことに興味を持って、自由にあそんで、チャレンジできる環境を作れると良いですね。